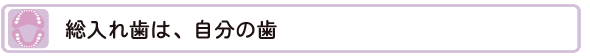
総入れ歯の歴史
年配の方々が集まると、まず「どっこいしょ」と言って座り、「もう歳だ、頭の毛はなくなるし、眼はかすむ、歯はぼろぼろだ」という会話が交わされます。若い頃にはビールの栓を歯で抜くことができた人が、40歳を過ぎた頃から歯が抜けはじめ、60歳を越えた頃には総入れ歯になったという話を聞きます。歯は失いたくないものですが、総入れ歯になる人は多いように思います。
はじめに、総入れ歯の歴史のお話しをします。
日本では、総入れ歯は1700年代後半、江戸時代から作られたであろうといわれています。当時の日本の総入れ歯は、世界に誇る独特の技術を持っていました。それはツゲという木を使って、顎の形にノミで削って合わせるもので、完成までにかなりの日数を要しました。この入れ歯が顎に吸い付く原理は、現在の入れ歯と全く同じだったのです。
一方、欧米では、1730年代から上下の入れ歯をスプリングでつないだものが作られました。この入れ歯は、顎に吸い付くのと違い、スプリングの作用で上下の入れ歯を開かせるものでした。入れ歯は顎に吸い付くものではないことから、日本の技術とは全く異なっていました。したがって、日本の口中医(歯科医)が作った入れ歯は、いかに優れたものであったかがお分かりと思います。しかし、入れ歯はごく限られた特権階級の人々のもので、一般市民には程遠いものでした。
さて、明治時代になって、ゴム床義歯が導入されて精度のよいものができるようになりました。そして、戦後に合成樹脂が入れ歯の材料として用いられるようになると、総入れ歯は一般的な歯科治療の1つとなったのです。ちなみに総入れ歯は、人が作った初めての人工臓器であるといわれています。
総入れ歯の問題点
つぎに、総入れ歯についての問題点を考えてみます。
上顎の入れ歯は、上顎を被うので味がわからないのではないか、また、下顎は馬蹄形をしているので、噛む度に動いて痛みを感じるのではないかと思われます。事実、総入れ歯の研究の歴史は、この2点の克服にあったのです。特に、下顎の入れ歯をいかに安定させるかが大問題でした。そのために色々な理論や技術が生まれました。
正直に言いますと、今日に至っても咬み合わせの理論がまだ確立されていないのです。でも、昨今の技術では、下顎の入れ歯が全く動かず、なに不自由なく食事ができるところまで進歩しています。とは言うものの、歯科医師に技術格差のあることは否めません。痛くて噛めない、口を開けると下の入れ歯が浮き上がって噛めない、などの不満があれば、別の先生を訪ねてみてください。きっと快適な入れ歯を作る技術を持った先生がいるはずです。
味覚の問題ではこんな研究がありました。
総入れ歯を入れる前と後で味覚がどう違うかという研究です。結論を言いますと、入れ歯をはじめて入れた直後は、確かに味覚の感覚は落ちるようです。しかし1〜2ヶ月も経つと、入れても入れなくても味覚は同じになるようです。人の体の順応性のすばらしさです。
とすれば、あとは入れ歯の安定の問題です。
入れ歯が安定するメカニズムは、先にも述べたように吸着作用によります。下顎の入れ歯といえども、食事中に動かなければ、食事のたびに入れ歯は粘膜に吸着します。そうすれば真に快適な食事ができるのです。今日ではそんな入れ歯ができる時代になっています。
入れ歯の安定剤について
入れ歯安定剤を常時使うのはお勧めできません。入れ歯安定剤のすべてとは言いませんが、常時使っていた患者さんの歯肉粘膜が、象の皮膚のようにブヨブヨになった状態を拝見したことがありました。そうなっては、入れ歯の吸着作用は全く期待できません。生涯にわたって安定剤を使用せざるを得ないでしょう。確かなことは言えませんが、粘膜に悪性の疾患が発症しないとも限りません。
入れ歯安定剤を使用しなくとも、入れ歯は確実に安定させられるのです。

